【5】抱えづかい人形 Bunraku Puppet
藤原玄洋(日本ウニマ事務局)文楽式の三人づかい人形や、車人形などのように、人形の後ろから抱えるようにつかう構造の人形。
棒づかいの人形のさらに発達したものと考えられる。一体の人形を1人でつかうものから、三人で
C図の人形は、右手はひじについた棒を握って操作する。左手も右手につながった糸により連動して
つかうものまで、さまざまなものがある。特に日本で発達した構造の人形であり、欧米では文楽
スタイルと、おおざっぱに呼ばれることが多い。
複雑な抱えづかい人形は無理としても、図15のような人形は比較的簡単につくれる。
B図の人形は、首についた胴串を左手で、人形の右では操作する人の右手に手袋をはめた手を直接
だして動かす。
右手は自分の手なので自由に物をつかむこともできるし、表情も自然にできる。
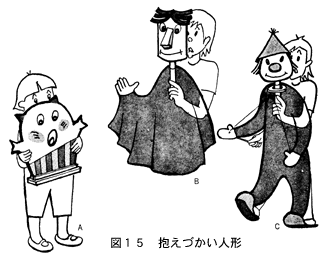
動く。人形の足をスリッパにすれば、足も同時に動かすことができ、舞台の上を自由に歩ける。
A図のような切り出しの人形で簡単に作ることもできる。
抱えづかいの人形は、直接両手にもって動かせるので、簡単な構造のものは小さな子どもでも無理
なく操作できる。また少し複雑なものなら、いろいろなしぐさができるだけでなく、人形がさらに
大きくなって扱いやすい。野外劇(ページェント)などのように、広い会場で大勢の観客に見せるに
も好都合である。しかも特に人形劇用の舞台を必要としないので、どんな会場でも大した準備なしに
上演できる。
また自分たちのシャツや服をそのまま人形の胴体にして作ることもできるので、首を紙皿等で簡単に
作れば、大勢の集会や、お祝のパーティの余興にも大きな成果をあげることができる。
目次に戻る| パペットパークに戻る